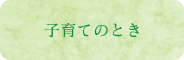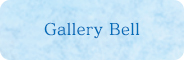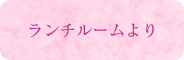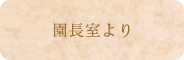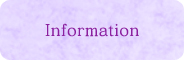子どもと本(10) 春をつげる鳥 鈴木 祐子
更新日:2021/04/21
まだ4月の冷んやりとした空気を感じる中、早い新緑の輝きと共に、子どもたちが、立派に進級、進学を果たしています。今年の季節の慌しさに追いつけないでいる私に、うぐいすが愛らしく鳴いて春を知らせてくれました。その声を聞いているうちに、この3ヶ月の間にBell祭・卒園式・進級式と続いてきたナーサリーの春が、私の中にやさしく沁みとおってきました。Bell祭のステージで小さい花組さんが歌った「うぐいす」のかわいらしい声が、心の中に響いてきます。
アイヌの伝説風に書かれた童話「春をつげる鳥」(宇野浩二 作)は、私が小学生の時に出会った作品です。名高く強いアイヌの部族長が、目の中に入れても痛くないほどに可愛がっている一人息子を自分よりも更に強く、勇猛な男に育てたいと思います。
ところが、その子がだんだん大きくなっていくのをみますと、やさしいばかりで少しも強くなりそうにありません。そして、他の子どものように山登りをしたり、うさぎ狩りをすることが嫌いで、そのかわり、木の枝や草の葉を小刀で切っては、それで笛をこしらえて、歌を吹くことが上手なのでした。
その頃の風習に従って、男の子が10才になった時、父親は、厳しい試験を与えます。それは山の小屋で何日間も食わず飲まずで過ごさせるというような厳しいものでした。何とか辛抱してほしいと願っていた父親は、5日目の朝、たくさんの食べ物を用意して、急いで迎えに行きます。けれども、体の弱い息子は、小屋の中で冷たくなっていたのです。
皆が深く悲しんで、息子の身体を埋めてやった時、何ともいえぬよい笛の音のようなものが聞こえてきました。それは、小屋の屋根にとまっているみどり色をした小鳥の声でした。その声は、死んだ部族長の息子が好んで吹いた笛の音に似ていて、こんな風に言っているように聞こえました。
「わたしは、いまは、こんな小鳥に生まれかわりました。わたしはこうして、
歌をうたっているときほどうれしいことはありません。わたしは、この歌で、
わたしのすきな人間の子どもたちに、春がきたことを、知らせる役をするつ
もりです。子どもたちは、わたしの歌をきいて、草つみにいったり、小鳥と
あそんだりする春がきたのだと知るでしょう。わたしは、春をつげる鳥…うぐ
いすです。わたしはなんという幸福な身分でしょう。」
これを聞くと、父の悲しみがすっかりやわらぎました。
自分に合わないことを強いられて、あんなに悲しい顔をしていた息子が、今は、生き生きとした、可愛らしい「春の使い」となって自分の身の幸福を歌っているのを聞くことができたのです。親としてどんなに安堵したことでしょう。できれば悲しい結末になる前に、子どもが人生を幸福に思えるような生き方ができるように見守ってやりたいと心から思います。私自身も春をつげる鳥…うぐいすの声を聞いて、美と平和を求める心が、益々強くなっていることを感じています。
4月にベル・ナーサリーの最後の施設が、塚田にオープンしました。
今から20年前、地元であるこの塚田・海神地域にすぐれた保育施設を作ろうという志のもとにベル・ナーサリーの活動は始まりました。これは、地域の子どもたちに責任ある幼児教育を行うために試行錯誤を重ねてきた当財団の実践研究の集大成です。
建物の外壁の色は薄いみどり色です。ここに、ナーサリー4園の子どもたちが集い、幸福な美しい人生の第一ステージを過ごしてくれることを願ってやみません。
春をつげる鳥
宇野浩二 作
講談社 現代日本文学名作集
子どもと本(9)雪の女王 鈴木祐子
更新日:2021/01/18
毎年、冬になるとどこかの保育室に必ず飾る絵があります。大きなゆきだるまとその横で楽しそうにしている女の子の絵です。今は、アスールの雪組さんのおへやに飾られています。
20年も前、雪が降った日に5才のこどもに水色の画用紙を渡しました。こどもたちは、そこにまっ白な絵の具で雪を描いたのです。この絵を見ると、降りしきる純白の雪を見て幼い心いっぱいに喜びを感じた瞬間が、今でも伝わってくるような気がします。
この時期に、ライブラリーの棚にいつでも手に取れるように飾られているのは「雪の女王」の絵本です。
悪魔の鏡のかけらが目に入ったために、ものごとを正しく見ることができない、或いは悪いところだけが見えるようになってしまい、冷たい心になった男の子カイは、雪の女王に連れて行かれてしまいます。仲良しの少女ゲルダは、カイを信じ、様々な苦難を乗り越えて、その優しい心で友達を救い出すのです。
「雪の女王」は、言うまでもなくアンデルセンの書いた有名なお話です。他の童話に比べるとずい分と大作なのですが、夢を見るような小さな物語が、次から次へと鎖を繋いだように積み重ねられていくので、子ども達は、夢中で、先生の読む長いお話に聞き入っています。
大人として読むと愛や死、永遠、人生のはかなさといったテーマが見えてきますが、子ども達には、すべての困難を克服して、カイの心をあたたかくとかすゲルダのやさしさがまっすぐに伝わっているのがわかります。
このお話の最後は、カイとゲルダが手を取りあって、二人が住んでいた町に帰ってくる美しい場面です。
カイとゲルダは、また手をつないであるいていきました。
ふたりが行くにつれて、あたりは、花とみどりにつつまれた
うつくしい春になりました。
二人は、いつのまにか自分たちが大人になっているのに気がつきます。そうして、二人は、雪の女王のお城に満ちあふれていた、ぞっとするような冷たいだけだった美しさを、いやな夢でも忘れてしまうようにすうっと忘れてしまいます。
こうしてふたりは、もはやおとなになって、そこにすわっていました。
それでもふたりはやっぱり子ども———心持においては子どもなのです。
そうして、季節はもう夏でした。
あと数ヶ月で、大きい花組さんは卒園し、小学生になります。毎日お外に出て、春夏秋冬の季節を身体いっぱいに感じることはできなかった一年間でしたが、そのような中でも子どもたちは確実に成長し、ものごとを感じる力をふくらませてきました。
今、目を輝かせて先生の読む絵本を見つめている子どもたち。その素直なやわらかい心は、いつか人間の真実と人間性の本質を洞察する、すぐれた力を自分自身の中に育てていく事でしょう。
大人になって、このアンデルセンの不思議な長編物語を活字を通して読むようになる子どもたちに、美しく輝く夏の光が、あたたかく恵みゆたかにふりそそぐことを願ってやみません。
雪の女王
アンデルセン童話集
山室 静 訳
子どもと本(8)クリスマス・キャロル 鈴木祐子
更新日:2020/12/21
花組さんが、自分たちで作ったオーナメントをツリーに飾り、月組さんは、毎日アドベントカレンダーを覗き込んで、今年も園内にはクリスマスを待つ子どもたちの笑顔があふれています。
ある日、ジングル・ベルを歌う子どもたちの声を楽しく聞きながら、私はふと胸に微かな淋しさを覚えました。終日マスクをしている自分は、長い間大きな声を出して歌っていない事に気付いたのです。
その日その日を無事に過ごすことに精一杯の私たち大人の歌声が、ナーサリーに響かなくなって随分久しいように思います。世界中を襲っている新型ウイルス感染症と、それに伴う自粛やシュリンクによって疲弊した感情が、世の中に広がっているのを恐ろしく感じる今、私は改めて一冊の古い本を開きました。チャールズ・ディケンズの「クリスマス・キャロル」です。
主人公の老人は、スクルージという名前ですが、これは英語でscrooge「守銭奴」とか「けちん坊」という意味のようです。強欲で情知らずのスクルージのところに、クリスマスの前夜、三人の幽霊(精霊)がやってきます。
最初は、過去の幽霊、二番目は現在の幽霊、最後に来る未来の幽霊それぞれに導かれて、スクルージは不思議な旅をします。
初めは、子どもだった頃の自分のクリスマスを思い出します。一人ぼっちで本を読んでいる少年のところに、楽し気にクリスマス・キャロルを歌いに来てくれた人たちのことを…。
次に、スクルージは、自分が低賃金でこき使っている事務員の貧しいけれどあたたかい家庭や、病気である幼いティム坊やを知ります。スクルージは自分の行いを悔い、何とかしてやれないかと思うのですが、現在の幽霊は、「無知」と「欠乏」の様相を示し、次に来る「破滅」を見せます。そして、これらを消さない限り、人間の世界に救いは無いと告げるのです。
その現実を知りながらも、冷酷に弱い人々を突き放してきたスクルージは、未来の幽霊に幼いティム坊やの死と、自分自身の惨めで淋しい死に様を見せられるのです。スクルージは恐怖に震えながら、未来の幽霊に「もし私が心を入れかえたならば、これまでに見せていただいた様々な影を、私にはまだ変える力があるのだとおっしゃってください!」と地面にひざまずいて訴えます。
クリスマスの朝、目を覚ましたスクルージは、自分の生き方を悔い改め、これまでに無かったような明るく楽しいクリスマスを迎えます。人間同士のやさしい愛情とあたたかい思いやりが何より大切だということを心から理解したのです。
この作品が書かれた19世紀頃のイギリスの時代背景、資本主義のひずみ、清教徒革命後に一たんは廃止されたクリスマスの風習…などを解説する文献は数多くありますし、私も若い頃ディケンズの作品と共にそれらを読んだ記憶が蘇ってきます。
けれども、今それらをすべて忘れて、精霊に導かれたスクルージと共に過去、現在、未来のクリスマスの旅をしていると、改めて自分自身を問い直す気持ちになってきます。
私が何よりも嬉しかったのは、最初にスクルージが自分の子ども時代を見て、懐かしい思い出や、やさしい気持ちを思い出した事です。これが、氷のように冷たい心をだんだん溶かしていく始まりだったのです。
私も自分の過去と現在と未来とをきちんと見つめて生きていけるようにしたいと思います。クリスマス・キャロルは「クリスマスの歌」という意味です。クリスマスを祝う習慣として欠かせないものです。大きな声は出せなくても、美しい心でクリスマスの素敵な歌をたくさん歌いたいと思います。
さて、このお話はティム坊やのこんな言葉で終わっています。
神様のお恵みが、
みーんなぜんぶにありますように!
クリスマス・キャロル
チャールズ・ディケンズ
脇 明子 訳
Merry Christmas
and
A Happy New Year
目に見える幸福、見えない幸福 鈴木祐子
更新日:2020/08/28
メーテルリンクの戯曲「青い鳥」は、1908年に発表されたそうです。それから100年以上の間、世界中の人々に親しまれてきました。原作を全部読んだことがなくても、青い鳥をさがして旅を続けるチルチルとミチルのお話を知っている人は多いでしょう。
その青い鳥は、幸福を表したものです。最近、私はこの戯曲をまたよく読むようになりました。
まほうの花園で、チルチルとミチルは、たくさんの幸福たちに出会います。チルチルが「あなたたちは誰なの」と尋ねると、みんなはどっと笑ってこう答えます。「わたしたち『あなたの家にいる幸福』ですよ。これからはもう少しおりこうさんになって、私たちを見つけられるようになってくださいな。」
「健康の幸福」は、一番美しいというものではありませんが、一番大切なものです。「清い空気の幸福」は透きとおっています。「両親を愛する幸福」は、あまり誰も相手にしてやらないので、悲しそうです。「青い空の幸福」や「森の幸福」、エメラルド色の「春の幸福」もいます。
やがて、もっと大きな「よろこび」たちがやってきます。「正しいことをするよろこび」「よいことをするよろこび」。「ものを考えるよろこび」のすぐそばには「もののわかるよろこび」がいます。他にも「美しいものを見るよろこび」や「ものを愛するよろこび」たちがいます。
そして、皆が手をたたいてひとりの「よろこび」を迎えるのですが、チルチルとミチルには、それが誰なのかわかりません。「かあさんだと思うけれど、ずっときれいなんだもの。」それは、「母の愛のよろこび」です。
おかあさんは、キスと抱っことやさしい笑顔でできたきれいなきものを着て、輝いています。目の中は星でいっぱいです。そして教えてくれるのです。
「おかあさんは、誰でも子どもをかわいがる時は、みんなお金持ちになるのよ。おかあさんの愛は、いつだって一番美しいよろこびなのですよ。」
結局、青い鳥はチルチルとミチルの家の中にいました。そして嬉しくてたまらないチルチルが、隣の家の病気の娘さんにあげようとしたとたんに、飛んでいってしまいます。
人間の幸福というものは、この青い鳥のように、つかまえて、ああよかったと思っているうちに、また遠くへ飛んでいってしまうものです。今は、幸福だと思っていても、それがいつまで続くものなのかもわかりません。
新型ウイルスがこれほど世界中の人々を苦しめる毎日が続くようになるとは、わずか数か月前まで誰も思わなかったことでしょう。
「コロナの時代を生きる」という言葉まで生まれ、人々に新しい生き方を示唆するかのような動きもあります。けれども、人が生まれ、何のために生きていくのかという意味においては、どのような状況にあっても大切なものが変わることは無いのだと私は信じています。メーテルリンクも生きていくことの意味をこの「青い鳥」の中で問い続けているように思えます。
毎日の暮らしの中で不便さや厳しさを我慢しながら、慎ましく、じっと楽しいことを「待つ」ことは、昔から私たちの中にある大切な心です。そこにこそ素朴さや素直さが生まれるのではないでしょうか。そして、そのやさしさやあたたかさの中に包んでやることが本当の意味で「子どもを大切にする」幸福ではないかと思うのです。
「安心」するということ 鈴木祐子
更新日:2020/06/15
梅雨時の雨に打たれながらも重たげな頭をしっかりと持ち上げて、紫陽花が美しく咲いています。薄紫や濃紫、水色や碧の微妙な色合いが不思議に混ざり合っている様子をクレヨン画に描いている子どもたちを見ているうちに、保育室に飾られているカレンダーに目がとまりました。「れいわがんねんど そつえんじより」……
この春、卒園した子ども達が作ったカレンダーの6月には、赤と青の紫陽花が大きく描かれていました。一つ一つのがく片や葉のぎざぎざまで丁寧に描かれた美しい水彩画の前に立って、私はもう胸がいっぱいでした。
2月末の小・中・高等学校一斉休校の要請が始まってからの保育園の日々を短い言葉で言い表すことは難しいです。常に心の深い深いところで続いている人々の緊張感、不安感が園内に得体のしれない不活発な空気を作り出していました。
一日一日を繋いでいくことに精一杯の私たちを励ましてくれるかのように桜の花が満開となり、難しい判断を迫られる中で、無事に開催できた卒園式。今も子どもたちとご両親の笑顔が浮かんできます。喜びと共に少しだけほっとした瞬間でした。
4月8日、政府の緊急事態宣言を受けて、船橋市長より登園縮小の文書が出されました。この日、ナーサリーでは「花まつり」の行事が行われていました。花まつりは、お釈迦様の誕生を祝う日です。色とりどりの花が咲きみだれ、池には白鳥が浮かんで、うっとりするようなきれいな景色の中で、安らかに誕生されたお釈迦様の話を聞きながら、子ども達は様々な色の紙でお花を作りました。
翌日から、ほとんど園児たちのいなくなった静かな保育園のそこここに、先生方は、その花を飾ったのです。
心配がなくて、心がほっとしていることを「安心」と言います。もともとは、弥陀の救いを信じて、心が安らいでいることをいう仏教の言葉だそうです。
今、私たちが最も求めていることは、心に不安が無く、心が静かに収まっていることではないでしょうか。
6月に入り、臨時休園が解除になって登園が始まることになった子ども達ひとりひとりのロッカーに、先生方は、花まつりで作ったお花を入れてあげていました。
誕生した日、七歩歩んで右手を高く上げ、「天が上、天が下、我ひとり尊きものぞ」と叫ばれたという釈迦の言葉を借りなくても、人間には誰しも何ものにもかえられない尊いものがあるのだと言うことを、今ほどそして、これほど実感したことはなかったように思います。
子どもがいつも「安心」していられるために、そばにいる大人は、いつも不安が無く、心が落ちついていられるようでありたいと強く願います。
子どもと本(7) そこの かどまで 鈴木祐子
更新日:2020/03/10
アーノルド・ローベルという作者の名前は知らなくても、「かえるくんとがまくん」のお話を一度は読んだことがあるのではないでしょうか。かわいらしく、生き生きと描かれる“Flog and Toad are friends”(ふたりはともだち)は、私を含めて子どもたちに50年近く愛されてきました。
その中に「そこの かどまで」というお話があります。
かえるくんが、まだおたまじゃくしとあんまりかわらないぐらいのころ、とうさんがはなしてくれます。
「むすこや、きょうは さむくって くもっているが、
いま はるは そこの かどまで きているんだよ」
早く春に来てほしかったかえるくんは、その「かど」を探しに出かけます。そして、小道を歩いてかどを曲がってみます。でも春はいなくて、
「まつのき いっぽんと こいし 3つ、
かれくさが すこし あっただけさ。」
かえるくんはがまくんにはなします。
どうしても春を見つけたいかえるくんは、いくつもいくつもかどを曲がってみるのです。でも春はどこにもいませんでした。すっかりくたびれてしまったかえるくんは、家に帰ることにしました。家につくと、そこにまたかどがありました。そのかどを曲がると、
「おひさま でてくる ところだったよ。とりたちが きにとまって
うたを うたっていた。とうさんと かあさんが にわで はたらいていた。
にわには はなが さいていたよ。」
何というやさしいお話でしょう。一生懸命に春を見つけようとしているかえるくん。そのお話を自分のことのように聞いていたがまくんは、
「みつけたんだね!」と叫びます。
はるが そこまで きているのを たしかめたくて、
ふたりは かえるくんの いえの かどを はしって まわったのでした。
何ものにも縛られず、何かの都合で曲げられることのないこんな子ども時代を過ごさせてやりたいと心から思います。人間の心は、経験を得ることによって成長していきますから、子どもたちがみずみずしい心で獲得した力ははかりしれません。
今、ベル・ナーサリーでは全ての子どもが、進級することへの期待と意欲をからだいっぱいに漲らせ、新しい一歩をふみ出そうとしています。そして、その一歩をあたたかく見守っているのは、常に身近にいる愛情にあふれた人たちです。春の訪れと共に芽生える力が、明日へと伸びゆくものの歓びを確かに育てていくことでしょう。
I was very happy.
I had found the corner that spring was just around.
とても うれしかったよ。
かどの すぐ そこまで きている はるを みつけたんだから。
「ふたりは いつも」より
アーノルド・ローベル作
三木 卓 訳
文化出版局
たえだえかかる 雪の玉水 鈴木祐子
更新日:2020/02/04
行きつもどりつしながら、春が少しずつ近づいてきています。季節の移り目はいつも、去りゆく時を惜しむ淋しさと、新しい季節を迎える喜びとが混ざり合って複雑な気持ちです。
寒のもどりがあって、身を縮こませながら歩いていても、空を見あげるとどこかにゆるやかなやさしい光が見えてきています。
まだ芽を出していない冬枯れの木々の枝も、ほんのりとした微かな赤味を帯び、来たるべき時に備えてじっと力を蓄えているようです。
いつの間にか季節は移ろうとしています。
山深み 春とも知らぬ 松の戸に たえだえかかる 雪の玉水
式子内親王
山が深いので、春が来たともはっきりわからない山家の戸に
雪どけの水がぽたりぽたりと間遠に落ちかかることよ
新古今和歌集の中で、私が最も好きなうたです。わずかに春の訪れを知らせる「雪の玉水」という表現の美しさ、ほのかなその兆しを喜ぶ心の中が、静かにそして確実に私の心を動かします。
現代は「わずか」とか「ほのか」とか繊細で優美なものは慌しく押し流され、賑やかに「オモシロカった」「モリアガった」ことが、充実した良い時間を過ごしたことのように思われがちです。
でも、本当に大切なものはそう簡単に姿を現したり、手に入ったりはしないのです。常に時と共にある「命」もそうでしょう。
子どもを育てていて、ふと気がつくと、こんなにも大きくなっていたのか、こんなことを考えていたのかと驚くことがあります。昨今の悲しいニュースを聞くにつれ、命が非常に軽く扱われていることに対して何もできない自分にもどかしさや焦りを感じます。このような時代にこそ静かな命への問いかけ、命へのやさしい眼差しは、子育てをする私たちに大切なことを教えてくれるような気がします。
ベル・ナーサリーも2月に入り、卒園や進級に向けて一段とたくましくなった子どもたちが、園内に明るい春を呼びこんでくれているようです。
賢者の贈り物 鈴木 祐子
更新日:2019/12/23
昔々、今から2000年も前のこと、新しい星がひとつ現れました。不思議に光る星でした。
その星をめあてに東の国からはるばると3人の博士が旅を続けていました。この世に救い主が現れる時は、不思議な星が輝く、昔の本にそう書いてあったのです。
大きな星は、ベツレヘムの町はずれの馬小屋の上で止まりました。馬小屋の中にはマリアが休み、側のかいば桶の中には、赤ちゃんがすやすや眠っていました。3人の博士は、救い主のお生まれになったお祝いに、たからものを差し上げました。
国中で一番だいじな宝石を
国中で一番とうとい乳香を(においのよいこうりょう)
国中で一番じょうとうな没薬を(たいせつなくすり)
この言い伝えから、クリスマスには、プレゼントを贈る習慣が始まったと言われています。
この時季には、キリスト者である人もない人も、プレゼントを楽しみにする大人や子どもが増えます。
「クリスマスには、○○を買ってね。」という声が私の周辺でもよく聞かれます。大人も、「プレゼントは何がいい?」と尋ねたりして、街の中でもそれを見越した商戦が繰り広げられています。
プレゼントは、日本語で言えば贈り物です。「贈る」は、本来「送る」と同じ言葉です。人に別れ難くてついて行った「送る」が、心をこめて人にものを届けるという「贈る」になってきたのです。この「心をこめて」が贈り物にはとても大切なことです。
親としては、子どもに何か買ってやりたいし、喜ぶ顔が見たいので、すぐ品物に目がいってしまいます。受け取った子どもも、欲しかった物なので、その時は嬉しいし、喜ぶでしょう。でも私は、贈り物に込められた「心」は別の姿で現れてもいいかなと思う時があります。
オー・ヘンリーの小説に「賢者の贈り物」という有名な短編があります。貧しいけれど愛し合っている若い夫婦が、それぞれに一番大切なものを売って、相手のためにプレゼントを買います。夫は、自分の大切な時計を売って、妻のために美しいべっ甲の飾り櫛を。妻は、自分の輝く長い髪を売って、夫のためにプラチナの時計鎖を……。わが家の最も大切な宝を最も賢くない方法で、互いに犠牲にした若い二人こそ、私には最も賢い人々に思えます。
ものは、いつかこわれたり、なくなったり、飽きたりしていきます。でも、それを贈った人の心が、あたたかく伝わるような、その時を思い出すと嬉しくなるような、そんなプレゼントを贈りたいし、贈られたいなと思います。
ギリシャの名医 ・・・へびつかい座・・・ 鈴木祐子
更新日:2019/08/07
子どもの頃、夕方になると涼み台に出て空を眺めるのが好きでした。昼間の暑さがやわらぎ、夜気がしのびよってくる空の色の変化を見ていると、様々な星たちが現れてきて、いろいろなお話を語ってくれました。
七夕で知られる織ひめとひこ星はもちろんのこと、大ぐま座、こぐま座、カシオペア座など、見つけながらわくわくしていたものです。
夏の星座としては、へびつかい座が印象的でした。屋敷うちに棲んでいる青大将と昼間出くわしたりした後は、特に気になって眺めたものです。
へびつかい座は、ギリシャ神話に出てくる名医アスクレピオスが天にのぼって星になったと言われています。…ギリシャ一の名医アスクレピオスは、知恵の女神アテナからメドゥサの血をもらいます。メドゥサというのは、髪の毛がへびで、その姿があまりにも恐ろしいので、一目でも彼女を見た者は、石になってしまうのです。勇士ペルセウスに退治されたメドゥサの血を、女神はアスクレピオスに渡してくれました。
「この血を病気やけがを治すのに役立てれば、 すばらしいことが
起こるでしょう。」
確かにその血の威力は大変なものでした。彼はその血を用いて死んだ人を生き返らせることさえできるようになったのです。けれども、人間が死ななくなれば、神をうやまう気持ちがなくなってしまうと案じたゼウスによって、アスクレピオスは命を落とします。…
すばらしい薬も、使い方を誤ればこんな悲劇が起こってしまうのですね。
使い方と言えば、最近は、公園などにある遊具が以前とはすっかり様変わりしました。私の子ども時代を含め、何十年もの間子どもたちを楽しませてくれた箱ブランコ、かいせんとう、シーソーなどが日本中から姿を消そうとしています。理由はいくつかありますが、これらの遊具による事故が各地で起きたことが、撤去される原因となりました。
けれども、これで危険防止になるでしょうか。遊具の使い方を学ばずに大きくなってしまった子どもたち。一緒に楽しく遊んであげなかった大人たちにこそ、問題はあるのでしょう。私自身も、子どもたちの「外遊びの安全」について、判断を迷う事が多くなってきています。
夜空に星が見えにくくなっていくだけでなく、昼間の遊びについても窮屈になっていく子どもたちの世界に心を痛めているのは私だけではないでしょう。医学のシンボルである大きなへびを手にして、アスクレピオスが何か言いたげです。
ことばの力は生きる力 鈴木 祐子
更新日:2019/07/03
ささの葉さらさら のきばにゆれる
美しいことばですね。さ音の連なりが笹の葉ずれの音と共に、子どもの成長を願う親の気持ちと重なって、やさしく響いてきます。また、軒端(のきば)という和語が、どこの家にもあったなつかしい風景を思い浮かばせます。
かわいらしい字で書かれた短冊、笹の葉にそれをつけている子どもの顔、昼の暑さがやわらいできて、夕方、涼風がたって葉がゆれ、天の川がしだいに輝きを増してくる・・・かつての夏の夕方の情景が、この短いことばから美しくやさしく浮かび上がってきます。
このようなことばを幼い時にこそ、たくさん聞かせてやりたいものです。人間の脳がこんなに大きくなったのは、ことばを獲得したからだと、以前ある本で読んだことがあります。たくさんのことばを持っているということは、たくさんの思考回路や感性を持っているということになります。これは、生きていく上で、お金やものをたくさん持っていることより、高い地位にいることにより、何よりも大きな力になります。
そのためには、どのようなことばをたくさん持っているかということも大切な問題になります。たとえば、子どもがことばを獲得していく過程を思い出してみましょう。あーあーという音からマンマー、ワンワンなどということばになり、やがてことばをつなげて「ママ来た」というような表現になってきます。そして徐々に微妙な気持ちの動きを表現したり、意見を明確に表そうとするようになるのです。
ところが、現在では、大人が擬態語や擬声語を乱発し、「ヤバい」等という一語を多発して気持ちを乱暴に表そうとしています。ことばが粗末なので、音量や文字の形状で変化をつけようとしたりしています。これは、大人の幼児化現象が起きてきたと言ってもよいでしょう。
語彙の貧困さや、時間をかけて言葉による表現を探していく習慣が失われてくると、それに代わるように「映(ば)える」という言葉が出てきました。今は、自分の気持ちを映像にして簡単に気持ちを表そうとするインスタグラムが大流行です。もちろん「インスタグラム」は商品名ですので造語です。Instant(すぐに・手軽な)Telegram(電報)を合わせたものなのだそうです。ここに大人が飛びついていくのは、「言葉の力」という意味において、生きる力の大切な部分が育っていないことの表れかもしれません。
私は、新しい感覚や時代によって生まれてくる「コトバ」を否定しているのではありません。むしろ、それを楽しみたいと思っています。ただそのためには、土台となる言葉の力が育っている必要を感じているのです。
日本には冒頭に紹介したような美しい子どもの歌がたくさんあります。私は、子どもたちにできるだけやさしい美しい表現で語りかけてやったり、お話を読んで聞かせたりしたいと思っています。そして、本来日本語が持っていたやさしさ、豊かさ・・・ニュアンスというものを自然に身につけ、
ささの葉さらさら のきばにゆれる
ということばを繊細に感じとれる大人に成長してほしいと思っています。今年は私も短冊にことばを書くのが楽しみになってきました。